学科テスト(仮免許前効果測定・仮免許筆記試験・本免許前効果測定・試験場での本免許筆記試験)を間近に控えているあなた!
最低限押さえておく言葉や意味を知りたいと思いませんか?
私が、以前教習生にお渡ししていた練習問題の表紙のところに書いていた内容をお知らせいたします。
又、今回は、ブログを書き始めたばかりですので、全般的なものにしておきます。
需要があるようでしたら、個々の教程についてのところについても言及し、覚え方のヒントや、語呂合わせ、間違えられやすい言い回し等についても述べていきたいと思います。
珍教官ブログの基本的な理念!
初めて、このブログをお読みになる方は、一度お読みください。この、ブログを紹介する方に、お知らせしている内容です。よろしくお願いいたします。
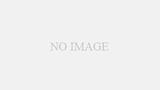
学科問題を解くポイント
親戚の子供が、とある自動車学校でもらってきた 練習問題集の表紙の裏に印刷されていた、「勉強のポイント」です。
ポイント①
例題1 自動車は、歩道・路側帯を通行してはいけません。
例題2 自動車は、歩道・路側帯をどんな場合でも通行してはいけません。
ポイント②
例題3 左右の見通しがきかない交差点(信号機のある交差点や 優先道路を通行中を除く)を通行する時は、一時停止しなければならない。
ポイント③
例題4 前の自動車が急に後退してきたので、やむを得ず 警音器を鳴らした。
例題5 前の自動車が急に後退してきたので、注意を与えるため 警音器を鳴らした。
例題6 前の自動車が急に後退してきたので、危険防止のため 警報機を鳴らした。
免許試験の問題文を読む時に、何度も出てくる理解しておきたい言葉!
私は、このサイトを作ってまだ間がないので、画像が貼れません。すみません。
言葉だけでお伝えしますので、わかりにくいかもしれませんが、ご了承くださいませ。
学科教本の「主な用語の意味」という項に書かれている言葉
まず、学科教本の冒頭にある「主な用語の意味」という項に書かれている言葉で大切だと思うものからピックアップしますね。
「車」に関する主な用語
・車など
車と路面電車の事です。
*という事は、路面電車は車ではないのです。(笑)
・車(車両)
自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスの事です。
*これは、不思議ですよ。(笑)。軽車両が「車」に入るのに、路面電車の方がどう見てもしっかりしてるのに、車などの「など」の扱いなのです。(笑)。軽車両には、ソリ、牛馬も該当するのにねぇ。
・自動車
簡単に言えば、運転免許証ですべての車が運転できる免許を取ったとします。その時に乗れる 車の中で、原動機付自転車を除いたものです。(原動機付自転車は自動車ではありません)
*私がよく言っているのが、「原付免許」が免許証の中に記載されているから、免許証の名称が、「運転免許証」となっているのだと。(笑)。原付免許が外れたら、きっと「自動車運転免許証」という名称になるのでしょうね。
「道路」に関する主な用語
・道路
(一部記載)一般の人が自由に通行できる場所です。
*キチンと整備されている道路ならば間違う事はないでしょう。しかし、気を付けて頂きたいのは、「一般の人が自由に通行できる場所」です。例として、校庭、公園、空き地、私道、境内なども入ります。
お年寄りが良く言っている、「昔は、運転免許は河川敷で練習して取得した。」と言う武勇伝は、今や通用しないのですね。因みに、自動車学校の練習コースは、公安委員会に届け出をしているので問題ありませんよ。でも、広大な会社所有のの駐車場等でも、違反になる可能性大ですよ。
・車道
車の通行の為に、縁石線、さく、ガードレール等の工作物や道路標示によって区分された道路です。
*では、校庭で運転練習するのはオッケーだと思いませんか?ダメなんです。運転とは、道路で車などを本来の用い方に従って用いることとされています。車道ではなくて、道路のなのですからね。
・歩道
歩行者の通行の為に、縁石線、さく、ガードレールなどの工作物によって区分された道路です。
*簡単に言えば、車が容易に入ってこれないように区切られて、歩行者の安全な通行の為に供された道路という事ですね。
・路側帯
歩行者の通行の為や車道の効用を保つため、歩道のない側に設けられた白線で区分された帯状の部分です。
*これが、車道外側線と間違えられるのですね。要するに、歩道の側にある白線ならば車道外側線。歩道がない側にある白線で区切られた部分は路側帯です。(笑)
車道外側線=歩道があるので路側帯の必要性が無い。車道外側線と歩道の間も車道とみなされるそうです???
路側帯=歩道が無いので、歩行者の通行の為に供された、白線の外側の帯状の部分です。
*車道外側線は白線のみの名称です。
路側帯は、白線の外側の帯状の部分です!
・交差点
十字路、丁字路、等二つの道路が交わる部分を、交差点と言います。交差点の縁石等は直角にとがってませんよね。通常半円形(1/4円形)ですよね。その縁の弧に当たる部分も交差点になりますのでご注意くださいね。
・横断歩道(自転車横断帯)
標識や標示により、歩行者(自転車)が横断する為の場所である事が示されている道路の部分です。
*横断する歩行者(自転車)最優先の場所です。検定で一番不合格者が出るところだと言われています・・・。
・優先道路
「優先道路」の標識のある道路又は、交差点の中まで中央線や車両通行帯がある道路の事です。
*道幅が広いか狭いかではないことに注意してください。
但し、標識も中央線も車両通行帯も無い所では、明らかに道幅が広い道路が優先になりますね。
・安全地帯
*車の通行が禁止されています。
・車両通行帯
車が、道路の定められた部分を通行するように標示によって示された部分です。
「車線」「レーン」とも呼ばれます。
*基本的には、正当な理由がない限りは、実践の標示は踏まないように私は指導しています。
破線の標示は、必要(目的)に応じて踏んでも良いと指導しています。
「道路に併設されているもの」に関する主な用語
・信号
あえて信号としたのは、警察官の「手信号」も含めたかったからです。(笑)
信号機=電気によって操作された灯火により、交通整理などの為の信号を表示する装置。
手信号=警察官や交通巡視員の手(又は灯火)による信号です。
・標識
道路交通に関して、規制や指示などを示す標示板の事です。
*一般に、電柱や鉄柱などの耐久性の高い棒状の先端に設置されている表示板です。
・標示
道路交通に関して、規制や指示 のため、ペイントやびょうなどによって路面に示された線や記号や文字の事を言います。
*そっかぁ・・・。「道路びょう」は、記号なのかな?(独り言)
「運転」に関わる主な用語
・運転
道路で車や路面電車をその本来の用い方に従い用いることです。
*道路の規定は教本に書いてあるけど、「本来の用い方」って、色々な解釈がありそうで、釈然としませんね。
・徐行
車がすぐに停止できるような速度で進行する事。(一般的には、制動距離が概ね1m以内の速度で、10km以下の速度であると言われています)
*多くの教官が、「10km以下!10km以下」と連呼していたなぁ。(笑)。( )内の言葉をいちいち言っていたら、支持が遅れるもんねぇ。
・停止
(この言葉は教本には出ていません…。当たり前すぎるのかな?)
*でも私は言います。停止とは、法令に従う場所と場合。危険を避けるためにやむを得ない場合に車を停める事だと経験上思います。
簡単に言えば(よく学科教習中も言っていました)止まらなければ警察官の手を煩わす可能性が高くなる、義務的な車を停める行為!
・駐車
車などが、継続的に停止すること(人の乗り降り、5分以内の荷物の積み下ろしを除く)や、運転者が車から離れてすぐに運転できない停止状態。
・停車
駐車にあたらない車の停止状態を言いますね。
学科教本に出てくる言葉で迷いやすい・間違えやすい言葉
数値に関する言葉
学科教習項目 13 「運転免許制度、交通反則通告制度」の自動車の種類のところに、
以下の、以上、以下、等がほとんど出ていますね。中型自動車の所では、こえる 以外がすべて、
二輪自動車のところでは、こえる が出ていますね。
・○○以上
その数値を含んで、更にそれを超える数値も。
・○○以下
その数値を含んで、更にそれを下回る数値も。
・○○を超える
その数値を含まず、それを超える数値のみが対象。
・○○未満
その数値を含まず、それを下回る数値のみが対象。
義務か?努力義務か?に関する言葉
・しなければならない。
「罰則有り」と覚えておきましょう。勿論文章が正当ならば〇です。
・した方が良い。
「現状罰則無し」と覚えておきましょう。
場所?・場合?
場所
・○○の地点
場所を表します。英語で言えば、where かな? 主にm(メートル)で示されることが多いですね。
場合
・○○の時
時を表します。英語で言えば、when かな? 主に時間や他の交通の状況に応じて使われる言葉です。
時間の場合は、秒で示されることが多いですね。
他の交通の状況ならば、必ず他の交通(車とは限らない)が存在しているはずですね。
教本の、「徐行」の項を見てください。
徐行すべき場所
と
徐行しなければならない場合
がありますよね。
これで、場所と場合が区別できますよね。
詳しくはこちらからご覧くださいね。↓
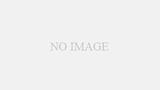
おすすめしていた学科試験対策勉強方法
実は、おはずかしながら、以下の方法を始めた頃、長女に勧めて、見事に失敗した経験があるのです。
長女は、大の勉強嫌いでした。
一番最初に家で、しぶしぶ練習問題に取り組んで答え合わせをしたときに、52点でした。
長女「お父さん、私、初めて解いた問題で、52点も取れたよ!天才かもよ」と言うのです。(笑)
私が、反応に困っていると、当時中学三年の次女がこう言いました。
「お姉ちゃん、馬鹿じゃないの?それって○×問題でしょ!なんの知識もない私があてずっぽで答えても、確率的に50点は取れるんだよ。自慢する事ではない!」と。
正に、次女の言う通り。
○×問題はあてずっぽでも、確率的に半分は正解するのです。
そこで、満足してしまう(自分に甘くなる)から、後々困るんです。
最初の解答の目的は、理解している問題と理解できてない問題の分別です!
免許試験の筆記試験は○×問題ですよね。
とりあえず、正解してたら満足する!というのはやめましょう。(笑)
半分の確率で正解してしまうのですから。
私は、このように勧めていました。実践した人が多くはいなかった気がしますが(笑)
まず、自信を持って答えられたものには、小さく鉛筆で○×を付けておく!
迷った(解答に自信が持てない)問題は、大きく鉛筆で○×を付けておく!
(迷った言葉にアンダーラインを引いておけば更に効果的)
(自分の考えを言葉に書けたら、更に効果倍増です!)
答え合わせをして、理解できていると判断した問題は、鉛筆で横線を引いて抹消する!
たまたま運よく正解した問題は抹消しない。解説を読み、解説に納得・理解したものだけを抹消する。必ず鉛筆で。(鉛筆なら消せるから)
二回目の解答の目的は、理解できてない問題の理解と記憶です!
横線で抹消されてない問題を時間を空けて解いてみる。
ここで、すぐに答え合わせをしないのです。
一度間違えた問題ですので、教本の関連するページを見つけて、教本を読んで、自分で答え合わせをするのです。
メリットは3つ!
こうすることによって、教本をくまなく見ることになります。
どこに、この答えが書いてあるかを探すことができます。
自分で答え合わせをすることにより、言葉の解釈の違いとかに気づきやすくなります。
何度も間違えたら、又は、よく理解できなければ、教本の文章の行間に、問題文を書き写す。
自分の手で書くと、より文章が頭に入ってきますし、記憶も確かになります。
教本での答え合わせに自信を持ったら、改めて、問題集の解答と解説を見るのです。
「自動車学校」でお悩みの方、次の記事一覧をご覧ください!。
「自動車学校」関連の記事が増えてきました。
この記事を読んでくださった方は、下記の記事もご覧になっています。
自動車学校について詳しくお伝えできれば光栄です。
・学科教習・筆記試験
・技能教習(一段階・二段階)
・検定
・教官
・口コミ
・ハラスメント
今まで私が質問された事や、悩んでいる事などについて、投稿しています。
よろしければ、お読みください。
一覧ですので、今、お読みの記事が含まれている場合もあります。
ご了承ください。
自動車学校への疑問!不安!知りたい事!珍教官が答えます!関連の投稿記事一覧!
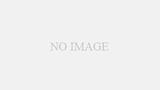

コメント